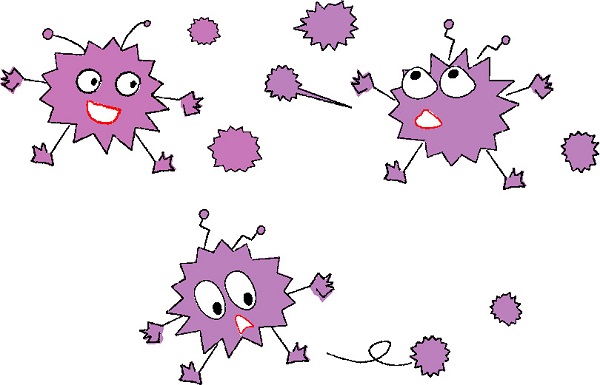約款(やっかん)というと、とても小さな字で細かなことが書いてあるものというイメージがありますよね。
これに対して契約書は、契約を結ぶ当事者の名前が書いてあったり、場合によっては署名や押印があったりするものというイメージがありますよね。
約款も契約書も契約の内容(中身)が書かれていることに変わりはありませんが、どういった違いがあるのでしょうか。
実は、現在のところ、契約書や約款については、法律に定めがありません。
そのようなこともあってか、現実にはあいまいになっていることもありますが、これらの違いについて説明していきたいと思います。
Contents
約款とは?
約款とは、たくさんの取引を画一的に処理するために、あらかじめ定型化された契約条項のことをいいます。
大量の取引をする場合に、いちいち細かな契約内容まで交渉していては効率が悪いため、あらかじめ定型化された契約条項を準備しておいて、契約を結ぶ行為の効率化を図ろうとするのが約款の役目ですね。
例えば、保険の契約をする場合に、非常に小さな文字で細かな契約に関する内容が書かれた冊子をもらうことがあるかもしれませんが、そのようなものが約款です。
あるいは、インターネット通販で商品などを購入する際に、細かな契約内容が表示されて「同意する」にチェックを入れるようになっていることがありますが、そのようなものも約款になりえます。

民法改正で約款の規定が新設!
冒頭でも触れたように、法律で約款については定めた規定はありません。そのため、これまで約款についてはあいまいなところがありました。
しかし近い将来(2020年ころ)、民法が大改正されることに伴い、約款に冠する規定が一部新しく定められることになりました。
ちなみに、民法改正全般の内容については以下の記事を参考にしてください。
新しい規定の主な内容は、「定型約款(ていけいやっかん)」といわれるものの規定の新設です。
定型約款とは、特定の者が不特定多数を相手として行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの(定型取引)で、契約の内容とすることを目的に準備された条項のことです。
個別に交渉することが予定されていない内容といってもいいかもしれません。
では、具体的にどのようなものが定型約款になる可能性が高いかというと、
- 保険約款
- 預金規定
- クレジットカード規約
- コンピューター・ソフトウェアの利用規約
などです。
ポイントは、不特定多数を相手として行う取引で画一的な内容であるものが対象になることです。
ですから、個別にみていくと、約款の中にそうでない内容が含まれる場合は、改正される民法の規定は適用されず、従来どおり個別に解釈されることになります。
ちなみに新民法では、定型約款の内容が不当なものであったり、相手方に不意打ちになるような内容である場合は、契約の内容にはならないという規定も追加されます。
約款と契約書などとの違いは?
では約款と契約書はどう違うのでしょうか?
定型約款と契約書との違いは比較的はっきりします。
定型約款は先ほどの定義のとおり、不特定多数を相手として行う取引の画一的な契約条項です。
これに対し契約書は、当事者が誰であるかや、代金の支払日がいつであるかなど、個別具体的な内容が書かれています。
ということは、誰と契約しても同じ画一的な内容であるか、契約者ごとに異なる個別的な内容であるかの違いがあります。
では「定型」が付かない約款との違いはどうでしょうか。
先ほども書きましたように、約款については、これまで法律に定めがありませんでした。
ですから、厳密な意味での定義はなされていませんので、完全な正解を答えることはできません。
ただ、これまで約款として一般的になされてきたイメージからすると、定型約款と同様に考えてもいいのではないかと思います。
法律に規定がないことで釈然としないと思われるかもしれませんが、契約についての根本的な考え方を理解すれば納得していただけるかもしれません。
契約に書面が必要な理由
契約と契約に関する書面についての基本的な考え方について説明します。
実は契約というのは、契約書などの書類がなくても当事者の合意のみで成立する(意思主義)ことになっています。
つまり、法律上契約は、当事者が口約束しただけで成立し、その契約に基づく権利や義務が発生するのです。
ではなぜ、契約に関係する書類が作られるのかというと、後で「言った、言わない」のトラブルを防ぐためです。

書類は証拠の役割を果たす
例えば、口約束で契約を結び、後になって当事者のどちらかが「そんなこと言ったっけ?」と言い出すと、口約束の場面を録音・録画していたなどの記録がない限り、契約があったことを証明することができず困ったことになってしまいます。
そのようなことにならないために、このような内容の契約をしましたということを書面にして、証拠として残しておくわけです。
効力が認められないこともある
ただ、契約についての書類があればどんな内容でも証拠として認められるかというと、そうではありません。
例えば、約款は冒頭でも触れたように、小さな字で細かなことがたくさん書かれています。
そこには契約についての大事なことがたくさん書いてあるんだろうけど、一度も読んだことはない!という方も多いのではないでしょうか。
しかし、そこに相手方にものすごく都合のよいことが書かれていて、自分にとても不利になる内容であることに後で気づいたとしたらどうでしょうか。
この場合程度にもよりますが、いくら書面で書かれてあっても内容が公序良俗に反する場合、その部分は無効になります。
それ以外に、内容が公序良俗に反しなくても、脅迫されている状態で契約書にサインさせられたような場合も、その契約書は無効になります。
ただ、契約書などの効力を否定するにはそのための証明が必要になり、それは容易なことではありません。
しかし、書類があればいつでも100%その書類の内容が認められるわけではないことには注意しておいたほうがいいでしょう。
書類の名称は重要ではない
以上をまとめると、契約を結ぶためには当事者の合意のみで足り、約款や契約書(誓約書、同意書なども含めて)は、契約をしたことを証明するために作成されるものです。
それらは、当事者が自由に作成するものですから、その書類にどんな名前がつけられているのかは、法律的にはあまり重要ではありません。
「契約書」という名前がついていない、あるいは別の名前がついている書類であっても、契約したことを表す内容であれば契約書と解釈されることがあります。
さいごに
約款(定型約款)と契約書の違いは、大まかに言うと前者は他の契約者とも共通する画一的な内容、後者は契約者ごとに異なる個別具体的な内容という違いがあげられます。
しかし、いずれも契約内容を証明する証拠となりうる点で共通します。
ですから、どちらも重要であることに変わりはありません。
民法の改正により、今後定型約款の規定が追加される予定ですが、実務的に大きく変化するというわけではなさそうです。
もっとも「定型約款」に当てはまる内容であれば、定型約款に規定が今後適用されることになりますので、その点は注意が必要です。